はじめに
開幕戦から根性を見せている新潟だが、結果が全くついてきていない。対するは、昨年のブレイクから今年はどうするの?と突きつけられている町田。昨年の徹底サッカーの対策をされたことで、昨年の繰り返しではタイトルは無理だ!と考えることは当然だろう。同じことをして異なる結果になることを期待してはいけないと、偉い人に言われたことがある。タイトルを狙わないならアゲインでいい気もするけども。
町田ゼルビア対アルビレックス新潟
新潟は3バックで試合に臨んだ。前節で稲村が怪我をしたことが大きいのかもしれない。起用できるセンターバックの陣容への不安と、町田の強力な前線をどのように抑えるか問題を考慮したのだろう。いざ!ミラーゲーム!!。町田も3バックで試合に臨んでいたので、新潟からすれば計算通りだったに違いない。
新潟の初手のゴールキックは蹴らされて失敗していた。その流れでクリアーミスを拾われて、町田に決定機を与えてしまうのだけど、藤田がチームを救う。立ち上がりとしては最悪の流れと言っても過言ではない。ここで失点していたらゲームオーバーである。
町田に目を移すと、下田がアンカー、前がビルドアップサポートを強め、西村がゴール前への飛び出し多めの役割分担で、ビルドアップ隊の枚数調整を個人の調整感覚に託しているようだった。
ただし、時間の経過とともに、というよりは、新潟のプレッシングのルールに合わせて、下田と前が横並びでプレーするように変化していった。下田たちで秋山たちを引きつけることができれば、セカンドボール争いで優位に立つし、ひきつけることができなければ、自分たちがフリーになりやすくなる構図となっている。
町田のプレッシングを観ると、相手陣地ではほぼマンマークだった。町田の普段の振る舞いがそうなのか、新潟の配置に影響されたのかは不明。下田と前で、秋山と新井泰貴を捕まえる意識は強めに設定されていた。相手の配置に関係せずに最初からマンマークで!と決まっていれば、新潟が3バックだろうが4バックだろうが、ほとんど意味はなくなる。
一方で新潟のボール保持の配置はよくわからなかった。ゲリアが右サイドバックのような位置取りをすることは準備されていたものなのだろう。逆サイドの堀米がサイドバックのような振る舞いをしていたけど、4バックと表現するには少ししっくりこない。なお、町田もドレシェビッチが岡村とセンターバックのように振る舞い、昌子が上がり気味な雰囲気であった。流行りの左右不均等なのか、シンプルに餅は餅屋現象なのかは不明だ。
町田の左右の攻撃を観ていると、林は少し下がり目で、相手を誘って裏に西村が飛び出す形が多かった。お互いが苦手分野よりも得意分野で勝負できるようになっているのだろう。左サイドは相馬、昌子、中山の元日本代表トライアングルアタックがメインのようだった。ちなみに町田の初手は谷からオ・セフンへのロングボールが多く、まずはオ・セフンへのロングボールを相手がどれくらい嫌がっているかのチェックタイムとなっている。
新潟の3バックビルドアップを見聞しようのコーナー
10分がすぎると、新潟もボールを保持して落ち着ける場面が出てくるようになる。面白いのがゲリアが右サイドバックとして振る舞い、秋山がセンターバックの間におりてプレーすることで、3バックを再現していることだろうか。
結局は3バックなら何の意味があるねん!と言いたくなるが、町田の守備は人基準への意識が強いのか、相馬単独の習慣なのかは不明だが、ゲリアの高い立ち位置によって、相馬が下がり、新潟のビルドアップ隊が息をできるようになっていく。しかし、この場面ではボールを奪われて相馬の決定機に繋がるのだが。
変化する新潟のビルドアップ隊に対して、【523】でプレッシングの雰囲気を見せる新潟だったが、町田も4バックへの変化を好んで行っているようだった。興味深いのは降りるエリアを作るために上がる昌子や降りる林だろう。昌子がいなくなることで、下田たちはプレーエリアを確保できるし、林が降りることで、岡村たちは立ち位置を移動することができる。
新潟を観ると、ゲリアが常にサイドバックのように振る舞うわけではなかった。マンマークを嫌がってプレーエリアを変更したい秋山たちからすると、ゲリアも含めた3バックの配置だと、プレーエリアが重なってしまう不運。このあたりのバランス感覚は阿吽の呼吸までになっておらず、3バックだからボール保持が機能しなかったと言われても無理はないだろう。
ビルドアップの出口として奮闘する長谷川や、今季のテーマである裏抜けによる速攻で谷口と4バックと変わらぬ現象もときどきは起こすことができていたことも事実だ。ただし、長谷川は相手を背負いながらの状況を余儀なくされたので、いつもより厳しい状況での出口仕事となったけれど。
恐らく最大の誤算は太田と藤原の関係性だったのではないだろうか。ゲリアが上がってくることで、大外から複雑な動きができそうな太田と藤原の関係性だったが、藤原が大外でボールを受ける場面が多く、お互いの良さが発揮できていなかった。
藤原ならばセントラルハーフの位置でもインサイドハーフでも働けそうなので、フリーマンとして動き回ってほしかったという無責任な願望を置いておく。途中で長谷川の秀逸なボールの受け方があった。そのタネはレーンを跨いだ動き。相手がついてくる可能性はあるが、本来いるべき場所から離れた場所に相手を連れて行く意味でレーンを跨いだ移動は長ければ長いほど相手をイレギュラーに追い込む傾向にある。
というわけで、生命線のセントラルハーフはマンマークで消され、バックラインの枚数問題の不安定さで彼らのプレーエリアの確保は不安定で、ビルドアップの出口になりえた長谷川も相手を背負っている状況で、逆サイドは役割分担が不明瞭となれば、新潟のボール保持が機能する場面が減ることも論理的な展開で。
それでも根性で繋げる場面はあり、20分には秋山のパスから谷口がダイレクトボレーで決定機。決めたらゴラッソだったけど、ゴラッソ製造ストライカーのイメージが谷口にはあるので、決めてほしかったという無茶振り。でも、前半はこの場面くらいしか記憶にない。
24分に町田が先制。ゴールキックからの繋ぎで秋山の無茶振りに味方が耐えられなくボールを奪われての速攻であった。相馬の縦突破からのクロスに西村が頭で合わせて町田が先制する。町田は目の前の相手に負けない!原始的なサッカーを披露。選手のクオリティは上がっているので、殴り合いなら負けない。個人的には西村のプレッシングのスイッチの入れ方が秀逸だった。
32分の西村のゴールが取り消された場面がこの試合の象徴的な場面だった。リードされたことで、前からプレッシングに行って蹴らせることに成功した新潟。しかし、オ・セフンに競り勝てない。こうなると、前から追いかけても意味があるのかないのか、となる。競り勝てないのはしょうがないとなれば、さらにプレッシングをかけてロングボールの起点を機能させないか、最終手段の相手にボールを保持させないが答えとなる。
本来の4バックに戻る新潟
後半の頭から森→矢村で【4231】に戻す新潟。初手から秋山へのシュートに繋がり、雰囲気は良さげ。初手が大事説はサッカーあるある。初手が良かろうが悪かろうが、しばらくしたら落ち着くんだけど。新潟の配置変更と初手の成功に対して、ちょっと様子を観るか!の町田の展開になったので、新潟がボールを保持する序盤戦となる。
リードしている町田からしても無理をする必要はない。相手のサイドバックの裏に相馬や西村を走らせる形でカウンターを仕掛ければOKという振る舞いに移行していく。お互いに意外だっただろうことは、なぜかオ・セフン周りは五分五分の状況へとなったことだろう。町田のセントラルハーフがセカンドボール争いに間に合わなく、慣れ親しんだ配置の新潟の下へセカンドボールがこぼれることが多くなった。
さらに、復活ハイプレッシング。矢村と長谷川が走りに走る。町田で西村が行っていたように、二度追いで相手を追い込みボールを蹴らせては前半よりは機能するようになっていった。その流れから61分には新井泰貴のスルーパスからチャンスメイクに成功する。徐々に町田のゴールに迫っていく新潟だが、谷を焦らせるような場面はまだ作れていない。
新潟の4バックへの変更に対して、相変わらず西村は前に出ている。相馬が調整役のようだった。西村の立ち位置にあわせて林も前に出てくるのだけど、すべての帳尻をあわせているのがドレシェビッチだった。自分のエリアが前にずれていくので、ためらわずに前に出ていくドレシェビッチは対面の相手に完勝であった。昌子も良い守備を見せていたが、ドレシェビッチのプレーエリアは広く、ついでにボールを確実に味方に渡していくので、手が付けられない。
70分に町田のクロス連打大会を凌ぐ新潟。試合は徐々にオープンな展開へ。ファウルも増えていくなかで、75分に桑山と羅相浩。なぜか漢字で変換される羅相浩。新潟も橋本、奥村、小見が登場する。残り15分で追いつけるかどうか。その小見、いきなり中山にちょっかいをだして笑った。
新潟のボール保持を観ていると、縦パスを後ろ向きで受ける選手に対してサポートをどれだけ早く行えるか大会の様相。これは開幕戦から続く新潟のデザインのようになっている。周りが助けられると、フリーでボールを受けられるのでターンすればいいだけなので、サポートの有無はそこまで関係なくなくなるけども。3バックではその繋がりが立ち消え、4バックでは少しだけ元に戻っていた。
そもそもそのためにはビルドアップ隊が相手をひきつける必要があり、そのためには藤田も交えてボールを繋ぎまくる必要もある。一方でそっち方面へ偏りすぎている昨年の印象から、今季は裏への意識も添えてのつもりが結果が出てなかったことを受けて混乱状態にありそうな新潟であった。小見の孤軍奮闘が目立ったが、ゴールに迫ることはできずに試合はそのまま終了する。
ひとりごと
町田は完璧な試合だったといっても過言ではなさそう。相馬や西村が移動すればセントラルハーフが突撃してくる仕組みもあり、3バックをつきつめている感に加えて、オ・セフンへの放り込みと、昨年のサッカーのミックス加減が絶妙だった。ただし、新潟の奇襲に助けられた面が大きかったことも事実なので、真価を問われるのはもう少し先に延期。
新潟は危機感ゆえの5バックだったけど、相手に利する形へ。前半から後半のようなハイプレッシングを!と眺めていたが、町田のビルドアップ隊の変化に面食らったのか、オ・セフンへのロングボールをリスペクトしすぎたのか、殴られ放題の前半戦となった。前半0-0なら計画通りだったのかもしれないけれど、町田のチャンスも多かったので、それはちょっと都合が良すぎなストーリー。次節でどのように振る舞うかの選択が山場になりそう。
ただ、余計な一言を行っておくと、3バックでも4バックでも機能性を変えずにボールを保持できそうなイメージが新潟にはあったんだけども。

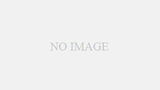
コメント