はじめに
パリ・サンジェルマンのサンジェルマンってなんだろうか。たぶん、何度か調べているはずなのに、いつも忘れてしまう。ってか、PSGが通称になると、サンジェルマンと呼ばれることも減るのだろうか。ちなみに、パリ・サンジェルマンとの出会いはライーがいたころになるだろうか。試合はほとんど見たことないけれども。
ちなみに、埼玉にはサンジェルマンという名のパン屋がある。
序盤戦はヤマル、ヤマル、ヤマル
スケゴーさんがヤマルについて呟いて炎上したことが記憶に新しいヤマル。恐らく、スケゴーさんは炎上したとは思っていないだろうけど。
そんなヤマルの華麗なドリブルのショーで試合の幕が開ける。序盤戦以外でもアウトサイドのスルーパスを連発し、チャンスメイカーとしても存在感を発揮していた。もしかしたら、ヤマルのなかでアウトサイドが流行っているのかもしれないし。普段から多用していただけかもしれない。
対面のヌーノ・メンデスを圧倒するのだから流石である。近いうちにバロンドールを取ることも間違いないだろう。アーセナル方面も左利きの逸材がたくさん出てきている。どうやら、世界は左利きを無事に育てきるメソッドを手に入れたのかもしれない。
スタメンの欠場が多いパリ・サンジェルマン。しまいにはアップでジョアン・ネベスが怪我をして、ザイール・エメリに交代していた。ザイール・エメリも個人的には好きな選手なので、あの3人に負けじと頑張ってほしい。
序盤のヤマルのショーのあとも、バルセロナが優勢のように見えた。正確に言えば、パリ・サンジェルマンが今日はどのような形でサッカーをすればいいかを探っている時間がいつもよりも少し長めに見えた。結論から言うと、バルセロナは普段着が最強だけど、パリ・サンジェルマンは衣替えを試合中にすることができる。この幅が試合の優位性の争いの決定打になった印象。
バルセロナは、フレンキー・デ・ヨング、ペドリのコンビが時間とスペースを配りまくり、サイドからはヤマルとラッシュフォードが質的優位を相手に迫っていた。ダニ・オルモとフェラン・トーレスも中盤のサポートをしながらゴール前に殺到ができるタイプなこともあって、パリ・サンジェルマンは何を優先して守ろうか画策する時間が続く。
普段着のパリ・サンジェルマンは、ファビアン・ルイスがどちらかというと攻撃的に振る舞う。でも、この試合ではビルドアップサポートを優先する形に変容し、ザイール・エメリが攻撃し、ヴィティーニャを助けるのがファビアン・ルイスになった。
ヤマルのために走り回るクンデの守備に奔走させられたバルコラ。懸命に守備をこなしていたが、いかんせん大変そうだった。攻撃面での狙いのほうが重視されていたけれど、守備面も考慮して、途中からサイドを入れ替えるようになる。クンデと比較すると、ジェラール・マルティンはそこまで複雑な動きはしない。
守備面でもワントップがセンターバックとゴールキーパーを見る形によるマンマークがパリ・サンジェルマンの普段着だが、ダニ・オルモとフェラン・トーレスがさすがに厄介だったのだろう。途中からビエルサ式マンマークに変更していた。ビエルサ式マンマークは最終ラインの枚数で+1を重視し、相手のセンターバックの片方はフリーにすることは仕方ないと割り切る形である。
ちなみに、パリ・サンジェルマン式マンマークとビエルサ式マンマークをスコアの変化やチームの疲れぐらいで変更する余裕をパリ・サンジェルマンはみせていた。このあたりの着替えはさすがである。ちなみに、バルセロナに先制されてからはパリ・サンジェルマン方式になっていた。
バルセロナはマンマークではないのだけど、ハイプレッシングはクンデやマルティンが相手のサイドバックまでプレッシングをかける京都サンガ方式なこともあって、マンマークに見えなくもない。マンマークじゃないんだけど。また、ミドルで構えると、ハイライン!を今季も惜しげもなく披露している。
パリ・サンジェルマンはシンプルな裏への飛び出し、裏への飛び出し二段構え、サイドチェンジでバルセロナに迫っていった。ただし、サイドからの質的優位はなぜかエンバイエが両サイドで良さを発揮。パリ・サンジェルマンはどれだけサイドで優位性を持ってこれるマンを揃えているのだろうか。ついでに、マユルのゼロトップも機能していた。
グリーリッシュのウイング仕草
皆様のチームはビルドアップで答えがみつからなかったときにどうしますか?キーパーに振り出しに戻るか、前に蹴っ飛ばすか、モドリッチのサリーに頼るか、などなど、各チームによってビルドアップで困ったときの振る舞いは決まっていると思います。
で、グリーリッシュです。マンチェスター・シティを離れてブレイクしているらしいグリーリッシュのプレーを早く見たい。見ればいいんですけど。で、グリーリッシュはマンチェスター・シティ時代にビルドアップでつまったときにお仕事を淡々とこなしていました。
そう、相手を背負って内側に切れ込み、攻撃をやり直したり、ボール循環のベクトルの向きを変えたり、相手を大量にひきつけて味方を自由にするグリーリッシュ仕草です。もちろん、グリーリッシュの専売特許なプレーではありません。サラーも普通にやります。家長もずっとやっています。ただ、ウイングのポストプレーのようでちょっと特殊なんですよね。
で、この仕事をバルコラが右サイドに移動して完璧にこなしました。バルセロナのプレッシングに対して、パリ・サンジェルマンは自陣深くでビルドアップを行うように段々と変化していきます。新しいゴールキーパーのシュヴァリエが普通に繋げることもこの選択を容易にしたのでしょう。ザバルニーがペナルティーエリアの横で普通にプレーしていた面白かったです。
で、自陣深くでプレーすることで、バルセロナの選手を自陣に引き寄せること。さらに、移動距離が長いバルセロナのサイドバックに長い距離のスプリントを判断と実行させること。で、バルコラんぼポストワークに神出鬼没のハキミたちを絡ませることで、より複雑になる右サイドで勝負すること。
ちなみにパリ・サンジェルマンの同点ゴールは長い距離を走ってきたクンデをヌーノ・メンデスが根性ではがしたことがきっかけ。このときにボールに対して守備をしていれば、あんなに長い距離を運ばれることもなかったのだけど。マンマークの弊害。マンマークじゃないんだけど。今は行ったり来たりだからねえ。
で、バルコラとハキミの仕事が本当に素晴らしかった。特に今の時代はフリーでターンでビルドアップの出口を見つけることはなかなか難しい。誰かが相手を背負いながらボールを受けて、そこからボール循環に変化を与えたほうが手っ取り早い。パリ・サンジェルマンはこの役割をいろいろな選手が手を替え品を替え。記憶が正しければ、パリ・サンジェルマンの逆転ゴールはイガンインのキープから始まっている。
バルセロナは60分すぎから守備のモラルがゆっくりと壊れ始める。たぶん、疲れたのでしょう。ペドリが相手のセンターバックまでプレッシングに出かけたり、途中からはプレッシングに出ていかなかったりと。だから、鬼の三枚替えでなんとかしようとしたフリックだったけれど、衣替えをしたわけではなく、半袖のままだったので、それで得点までたどり着けるような相手ではなかった、という試合でしたとさ。
ひとりごと
このメンバーでも勝つんかい!というあたりに自信の大事が伝わってくるようなパリ・サンジェルマン。だって、クバもデンベレもドゥエもジョアン・ネベスもマルキーニョスもいないのに普通に勝つんじゃない。
バルセロナは片翼飛行感が少し。でも、ラッシュフォードも別に悪くなかったので、片翼ではなかったのに、その感じが少し。エリック・ガルシアが元気なことは良かった。

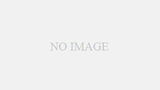

コメント