はじめに
欧州サッカーが無事に終わりましたとさ。今年はレバークーゼン、ボローニャ、ジローナのサッカーに魅了され、終盤にローマとスポルティング・リスボン、フェイエノールトも良いサッカーするやん!と気がついた2023/24シーズンとなりました。飽きっぽい自分は同じチームを追いかけることは無理!と完全に気がつかされた一年でもあり、来年はどうしてやろうか?と考えるこの季節は楽しいもんですね。
いつもだったら、気になった選手イレブンとなるんですが、今回は23/24シーズンを通じて、気になった戦術みたいなものを羅列して行こうかなと。戦術みたいなものとした理由は特にありません。現象から探っていく派閥なので、様々な現象を振り返って置くと、未来から見たときにこの記事が面白くなるかもしれないなーという淡い期待。
お出かけするCB
自分の拙い記憶を探ってみると、お出かけするCBを初めて見たのはベティスのバルトラだったような。当時は偽SBがアラバロールと呼ばれていたこともあって、一部界隈ではバルトラロールと呼ばれていたと記憶している。確か3バックだったベティスにおいて、中央を担っていたバルトラが突然にアンカーの位置に移動する仕掛けだったような。もしかしたら、ゴールキックの場面だけだったかもしれないけど。順番としては偽SBのあとに登場したので、偽CBまで起きるのか!みたいな流れで整理されていたような。
現代のサッカーでは3バックの片割れの攻撃参加、正確に言えば、3バックの片割れがSB化する作戦は一般的になってきている。なお、この流れをさらに加速させたチームはインテルだ。ときどき3バックの全員が中盤に移動し、CB以外の選手たちがビルドアップ隊としてキーパーの側でプレーするレアな状況が成立して今季は話題になっていた。ビルドアップにはマンマークで対応がデフォルトの世界において、マンマークならポジションチェンジが定跡としても、CBを交えてやるんかいとう衝撃は異常だった。
CBのお出かけはまだまだ止まらない。SBにボールをつけるCBは、普通は斜め後ろにサポートをする流れがあるのだが、近年はSBからのワンツーをもらうためにがんがんSBを追い越す動きを行う。相手がついてくれば、キーパーへのパスラインができる段取りになっていて、相手がついてこなければワンツーが成立する二段構えは多くのチームで標準化されたプレーとなってきている。SBを追い越すなんて!となりそうだが、追い越したほうがリスクが少ない現実がすぐそこまで来ている。
お出かけするCBで象徴的なケースは、4バックのCBがお出かけだ。二人共にいなくなるケースはまれだが、CBの片割れがお出かけすれば、SBを含めた形でビルドアップ隊が形成される。すると、SBをマンマークで担当する相手は少し困った形となる。SBは高い立ち位置を取ることもあれば、中盤化することもあれば、深い位置でCB化することもあるとなると、これらの動きに対してマンマークで対応は机上では可能だが、現実では少し難しい。マンマークの選手がどこまで連れて行かれるかわからないからだ。
猫も杓子もサリーであるならば、最初から相手の配置を3バックと仮定して対策をすることは可能だろう。しかし、最近の可変は何をトリガーとしているか怪しい雰囲気に満ち溢れている。チャンピオンズリーグのファイナルにたどり着いたドルトムントも【433】と【325】を使い分けていたくらいだ。レアル・マドリーで言えば、クロースの降りる位置がCBの間なのか、CBの脇なのかでも、相手からすればだいぶ異なるのが現状だろう。言葉にすれば臨機応変に状況に応じて!となるが、そういったことに対してその場で判断を繰り返していくことは現代サッカーの肝とも言えるかもしれない。
ビルドアップにおける空白のレーンとマイナスの概念
5レーンを埋めようぜ!時代に突然に登場した空白のレーン。もともと5レーンを埋める5トップに対して5バックで待ち構える作戦へのカウンターとして誕生した感のある空白のレーンだが、今回の空白のレーンはビルドアップのお話となる。マンチェスターシティの得意技だが、CBがお出かけをすると、CBのいたレーンが空白となる。本来なら3バック化し、レーンを均等に埋めるのだが、そのまま空白を維持することで歪みのある形でのビルドアップをスタートすることが多い。
空白のエリアにはロドリが降りてきたり、エデルソンが前に出てくることは、おなじみの景色ではないだろうか。このように、空白のエリアへの出入りをすることもあればしないこともあることで、自分たちの形をできるだけ定まらないようにしていることが要チェックポイントとなる。CBのお出かけでも触れた自分たちの形をさだめないことで、相手の対策を無限地獄に追い込むことも狙いの一つだろう。
左右対称に配置されるプレッシングの配置に対して、ボール保持側の配置が非対称になると何が起きるか。どこかでマイナスとプラスが発生していて、地味にマイナス側にも非対称のメリットが生まれることがビルドアップにおける空白のレーンの醍醐味になっている。なんにせよ、いるべき場所に相手がいないことは守備者からしても迷いを生むことは明白だからだ。例えば、【325】の【2】。一人がアンカーとして振る舞えば、もうひとりの選手はどこに移動しても、そのエリアがプラスになると同時に、その選手がいないサイドはマイナスとなる。
傾向としてプラスサイドはオーバーロード、マイナスサイドは空白のレーンとアイソレーションを組み合わせていることが多い。オーバーロードは選手が多いので好きにやってくれや!でいいけれど、枚数が足りない方にはそれなりの何かが必要である。各々が上手であることは言うまでもないけれど、空白のレーンで相手の対応をぼやかし、そのレーンへのサポートでマイナスをゼロにしやすいことも応急処置となっていることがポイントだ。CBのお出かけと比較すると、配置でどうにかしようとする派閥の得意技となっている。
再評価されるピン留め
ピン留めも漢字が正しいのかわからない。簡単に言うと、相手に守備に基準点を準備することで、他の誰かをフリーにする手法である。わかりすいのはハーランドを最前線に鎮座させることで、ライン間でフォーデンを躍動させる作戦。アルバレスが最前線だと、スペースメイクとスペースアタックに様変わりする。これも流行りといえば流行り。
猫も杓子も【325】だが、【235】もゆっくり見ることが増えてきた気がする。【235】は普通の【433】やないか疑惑もあるのだけど、肝はハーフレーンに選手が縦視点で見ると並んでいること。悪名の強い原則になってしまった感のある「隣り合うポジションは同じレーンにいてはいけない」だけれど、ちょっと前のリヴァプールを例に出すまでもなく、最近は同じレーンにいることで、どちらかをフリーにする段取りが増えてきている。
ロドリの解放がアンカーではなく、ダブルピボットだとすると、ライン間職人の解放が【235】の【3】の部分にある。この位置に3枚が並ぶことで、相手の3セントラルは前におびき出される、守備の基準点が準備される形になる流れとなる。いやいや、1列目に走ってもらおうぜとなるかもしれないが、2枚のCBも控えている状況なので、相手の無限ポゼッションの実現に拍車をかけるだけ。誰かが降りれば【32】になるし、外に広がれば【41】ビルドにもなるわけで、対策は無限となる。ほら、サイドで質的優位が得られないならば、サイドは囮で中央が本当の狙いみたいな。でも、それが後述する【撤退442】を生んだ感も。
中央3レーンアタックもハーランドのようなCFがいなければ、ワントップツーシャドウ的な運用ではなく、ツートップ+トップ下のような運用もツートップによるピン留めでトップ下の解放となる。なお、この場面でツートップの片割れがいないからといって、迎撃が可能か?というと状況による。特に中央3レーンにおいては空白だからといって、持ち場を離れていいのかどうかは非常に怪しいところである。ゼロトップが猛威をふるったように。
6人目のアタックへの6人目を準備するいたちごっこ
5レーンアタックに対して、5人を並べる5バックがデフォルトになってくると、今度はその対策が生まれる流れとなっている。たぶん、最初はテンハーグのアヤックス。ほとんど6人を並べることもあったが、基本的にはボールサイドへの密集で優位性を持った状況で相手の最終ラインをブレイクすることを狙った。なお、【442】をデフォルトとするチームは、サイドバックがウイング化すると、6トップのようになるので、5バック対策として一部で流行っている。
カンセロの突撃が話題になったように、5トップからの離脱によるマイナスをカンセロの突撃でプラマイゼロにする流れは今でも多くのチームで採用されている。なお、マンチェスターシティはストーンズのインサイドハーフ化によって、前線に6枚を揃えることで、5レーンアタックとライン間を同時に実行しようと画策していた。
となると、どうやって守るか。ハーフスペースの防護を3バックの両脇に任せる形が5バックのデフォルトである。しかし、6人目が強襲してくるとなると、どうするか。答えはシンプルに人海戦術となった。アーセナルはサイドハーフを守備に参加させることで、サイドバックをできるだけペナ幅から出さない作戦を使い、レアル・マドリーはセントラルハーフにハーフスペースの防護を行わせることで、相手の6人目攻撃への手当を実行した。
ついでに1列目の選手たちが相手のセントラルハーフを抑えることに尽力することで、レアル・マドリーはセントラルハーフが守備に集中することができる流れとなっている。アーセナルはセントラルハーフを中央から動かさずにいざとなったら最終ラインに加わることで、サイドからのスライドによる穴を防ぐ計算となっていた。結果として、マンチェスターシティを徹底的に苦しめた作戦が【442】による撤退であったことは少し面白い現象となっている。
そんなに撤退して大丈夫なの?となりそうだが、トランジッションのデュエル勝負で勝ちまくったウィルシャーを例に出すまでもなく、レアル・マドリーとアーセナルにはタレントがいるし、なんなら最終ラインからボール保持を実行しそうな雰囲気すらある。6バックはかつてのモウリーニョがどこかでやった記憶もあるが、撤退守備からのロングカウンターや、相手に押し込まれた状態からでもボール保持を回復できるチームにとってはバスを止めるだけの作戦ではない。それだけ警戒されるマンチェスターシティが異常なだけかもしれないけれども。
ミドルプレッシングからハイプレッシングへの移行の罠
チーム森保の得意技である。相手の選択肢を削り、特定のパスをスイッチにミドルプレッシングからハイプレッシングへ移行をすることは多くのチームが行っている。ハイプレッシングやマンマークによるプレッシングへの対策は、同数なら前線に蹴っ飛ばすがデフォルトだが、ゴールキーパーまでプレッシングに行くべきか否かは多くのチームの悩みの種だろう。
イラク代表が日本に仕掛けたようにゴールキックはセンターバックにつける→ゆっくりと運んで裏まで蹴っ飛ばす作戦に苦しめられたように、繋ぐふりをする→相手が前に出てくればロングボール。相手が前に出てこないならば自分たちに優位な配置と出発点からの攻撃と二段構えになっていることがにくい。
また、マンマーク志向のチームはどうしても相手のサイドバックに対して、自分たちのサイドの選手の縦スライドで根性で対応するチームが多い。根性では無理なので、サイドバックにロングボールをつけるチームが多いのだが、同時にサイドバックのセンターバック化への対応がめんどくさいことは同時によくわかるだろうか。え、あんな位置までサイドバックのおれがスライドするのか??という悩み。
レアル・マドリーは裏への選択肢をロドリゴ、ヴィニシウスで、空中戦の的としてベリンガムとバルベルデを準備していた。残りの選手はビルドアップ隊なので、割合は【6:4】と言えるだろう。このバランス感覚がにくい。最終ラインを世界屈指のセンターバック軍団で揃えているマンチェスターシティを相手にしても、この4枚がそれぞれの位置で競り合いを行い、相手のプレッシングの枚数が少なければ、6枚+キーパーでボールを回し、サイドバックを逃げ場とする作戦はハイプレッシングの限界を示していた。
同数なら放り込むでマンチェスターシティはハーランドしか選択肢がなく、ハーランドが負けたら終了となるが、レアル・マドリーは4人がばらばらに有機的に動き回ってロングボールを受けるのでまじで厄介であった。マンチェスターシティはボール保持の改善で事無きを得ることなったが、レアル・マドリーにつきつけられた課題は、来季のプレミアリーグで多くのチームが真似をするかもしれないし、レアル・マドリーしかできない芸当だったのかもしれない。ちなみにハイプレッシングをやめ、ミドルプレッシングで耐えようとすると、クロースとヴィニシウスの無限チャレンジと向き合うことになるので、それも罠。
ボール保持者中心主義
ラストである。ポジショナルプレーの可視化によって、全体の配置を整えるチームが増えてきている。もちろん、中央圧縮攻撃なんだぜ!のチームも例外でなく、それぞれのチームが選手に対して、それぞれの初期配置を割り振っているのが現状なのではないだろうか。エリアごとに役割が割り振られ、移動する選手たちはたまたま出会したエリアごとの役割に従いながらも個性を乗っける時代とも言える。
しかし、オーバーロードの流行りによって、配置が整っていないことが受けいられるようになってくると、ボール保持者へのサポートを潤沢に行うチームが増えてきている。バランスの維持された全体の配置からボール保持者へのサポートを配分していくのではなく、ボール保持者周りのサポートを決めて、その後に全体に派生していくパターンと言うか。
かつてグアルディオラの伯父貴がボール保持者の斜め前、斜め後ろ、左右にサポートがいれば最高と言っていたが、これに相手の配置を条件として入れ込んでいくと面白い。ボール保持者の実際には左右両方に避難場所を作り、あとはギャップに選手を埋め込んでいくだけ。ギャップの考え方も縦視点だけでなく、横視点を入れたり、サイドラインを点と考えたり。
なんにせよ、ボールを失わなければいいし、ボール周辺から得た時間とスペースを紡いで行けば良いので、人が多くてもいいやんという考え方は素敵な一方で、どの段階でオーバーロードを行うかはまだまだチームによってばらばらである。
ひとりごと
つらつらと書いてみたけれど、まだまだ試作品のような内容も多いので、有料noteにするのも手だったか、、と書き終わって気がついた。けれども、もう手遅れ。来季はどんな新作に出会えるのか楽しみなんだぜ。
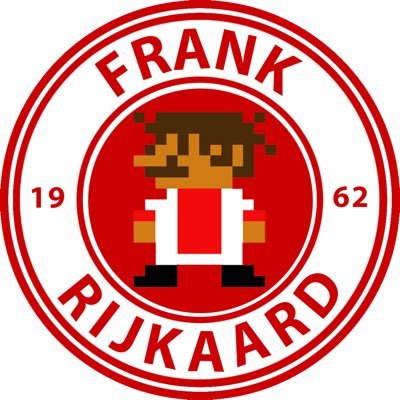


コメント