昨年に数試合だけ行ってきた短観シリーズをできるだけ今年はやりたい気分なのだ。J1を全部観ることは無理だが、4試合くらいは観られるのではないかと。観戦は計画的に。昨年は途中からフトチャンの分析記事に集中となったことで、短観シリーズが終了したことは誰も知らない。なお、今年もフトチャンの分析シリーズはあるのかどうかは乞うご期待。
ヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島
FUJIFILM SUPER CUP2025です。熱心な読者の方々ならおわかりだと思いますが、ぼくは記憶力があるようでありません。どうでもいいことは覚えていますが、大切なことはすぐに忘れてしまいます。というわけで、この試合はもう忘却の彼方感があるのですが、構わずに書いていこうと思います。
最初にスタメンがらしいなあと感じました。ヴィッセル神戸はためらいもなく2チームの準備をすすめ、サンフレッチェ広島はいつだってベストメンバーのスタイルだったことは、両チームのらしさを存分に示したスタメンだなあと。
ヴィッセル神戸に目を移すと、齊藤未月が元気な姿に安堵し、冨永虹七が面白いなあと感じさせられたぐらいで、大迫、武藤、扇原、酒井高徳が作り上げたサッカーを再現するには若手だけではまだまだ難しいと証明したわけです。まあ、相手が悪いだけ説もありますけど。
特に気になったのはボール非保持の場面。ボールサイドへの圧縮で相手のボール保持に対抗する印象が強いヴィッセル神戸でしたが、このメンバーではその圧縮とボール保持者への圧力も少し足りないというか。
スペシャルな選手やベテランがいないことで守備だけはサボりません若手だもん、みたいな構図ってあると思うんですけど、ボール保持よりも非保持が良くないんかい!というのは、監督コーチ一同にとって計算違いだったのではないかなと。ただし、先日のACLでも観られたように、ユース出身者を強引にでも起用していくスタイルは今後のJリーグでの広まっていくのかもしれないなと。そうしないと、みんな海外に行っちゃうからね。育成の早送りであります。ACLでの里見くんのベンチ入りはびびった。
基本的には初瀬がいなくても昨年と同じスタイルでやるんかい!というところにヴィッセル神戸のたくましさを感じたんだぜ。3バック化と対角へのロングボール。浦和戦も含めてロングボールの起点と同サイドの攻略が少し機能しなかったことが痛かったなかなと。
ベストメンバーでヴィッセル神戸を寄り切ったサンフレッチェ広島は、マイナーチェンジも特にない印象。試合に出ている選手の個性がピッチへの影響が半端ない印象はあれど、昨年同様にハイプレと速攻がメイン。ただし、中島洋太朗とアルスラーン戦記だけ時空間能力が半端ないみたいな感じ。セントラルハーフを横並びにしてバランスを確保しようぜ勢の希望を打ち砕くように、セントラルハーフの片方の飛び出しは健在で、セントラルハーフが出ていかなければ、センバが出ていくわけで、スキッベ監督のやろうとしていることが決して外野の思い通りにはいかないところが素敵。
ただし、基本的には昨年のリサイクルになるので、弱点も一緒。3バックに代わりとなる選手が出てくるか問題はさることながら、個人的には加藤、ジャメが大橋の穴を埋められるかが優勝できるかどうかの鍵を握っていそう。つまりは決定力と得点力。アルスラーン戦記がそれを解決し続けるというのは少し都合が良すぎるような。がんばれ満田誠。
ガンバ大阪対セレッソ大阪
昨年の感じからすれば、ガンバ大阪の圧勝になりそうなところが結果はまさかの裏返しと。たぶん、みんながびっくりしたに違いない。ぼくもびっくりしました。
昨年の継続だろうなと勝手に思っていたガンバ大阪だけど、マイナーチェンジを敢行。こんなにハイプレだったけ?とか、ボール保持の配置はこんなに自由だったけ?と少しの驚きと混乱を提供してくれましたとさ。この試合の分水嶺は、ガンバ大阪の狂気のハイプレに対して、セレッソ大阪は相手がハイプレしてきてくれないかなーと、待ち構えていたことなのではないしょうでしょうか。不運な組み合わせ。畠中と香川にプレッシングを回避され続ける運命になるとは試合前には想像もしていなかっただろう。
それでも段々とセレッソの配置に対して対応をしていくガンバはお見事だったけど、サッカーでときどき起こる行事である相手の決定機がなぜかほとんど決まってしまうでござるの法則が寄りにもよってダービーで発動。そういう意味ではマイナーチェンジと相手の決定機がなぜか入ってしまうの法則とかみ合わせに結果が引っ張られすぎた印象。失点を観ると、2点目と3点目はなんでそうなるねん!と言いたくなるのではないだろうか。
ハイプレの精度やボール保持の決まり事を昨年に戻す?などなどと次節の楽しみはたくさんあるが、マイチェンをする理由は必ずあると思うので、ガンバはこの方向性がどうなるか観てみよう案件。
セレッソ大阪はポステコグルー一派らしい意地でもつなぐ姿勢や、突然の偽サイドバックやサイドから強襲するウイングと自己紹介に成功。繰り返しになるが、畠中と香川がキーマン。このコンビがいなくなったときにプレー原則で解決できるかは未知数。個人的にはハットンの周りと繋がり続ける姿勢に驚かされた。もう少しセルフィッシュでもいいと思うくらいに。
点差もついたので、ポステコ名物のハイプレはそこまで発動せずに、442で中央圧縮のミドルブロック。ガンバ対策かもしれないが、中央圧縮が過ぎてサイドからがんがん前進を許し、クロスまでたどり着かれる場面が多かったような記憶があるので、この部分を相手がどのように利用してくるのかどうかは楽しみにしておきたい。自覚的だから最後は541にしたのかもしれないけど。付け加えると、阪田澪哉もすごく良かった。
ヴィッセル神戸対浦和レッズ
ほぼベストメンバーのヴィッセル神戸対蓋を開けてみないとどうなるかわからない浦和レッズの勝負。昨年もいい試合だった気がする。本当にそうだったかは覚えていないけれども。
新生と言いたくなるが、別に新生ではない浦和レッズが少しおもしろかった。ヘグモ時代は絵を揃えてプレーできていたというよりは、絵を揃えていこうぜ感の強いボールを保持するサッカーだったけれど、スコルジャになって絵は揃っているんだけど、ピッチでは原始的なサッカーが展開されるという罠。センバがボールを持っているときに今までだったらパスコースないやん、、、って困りそうな場面でも、全く困る素振りもなくロングボールを選択している場面が印象に残っている。
ボールを保持したときに433ちっくになることもあるんだけど、本質はそこではなく松本泰志の分身の術がすごい。トップのチアゴを追い越す動きで裏抜けを連続で行う。内側に移動するサビオのために大外に移動する。トップ下の仕事をまっとうすると役割が多岐にわたっていた。サンフレッチェ広島でも見せていた分身の術を浦和レッズでも惜しみもなく披露。なお、広島では川辺が分身の術にチャレンジしているらしい。
そして金子とサビオの能力が段違い。ボールが収まり仕掛けることもできるので、サイドバックの攻撃参加だけでなく、渡邊凌磨が飛び出してもリスクが大きくならない。なので、ただでさえ能力の高いウイングコンビへのサポートが絶え間なく行われるので、金子はクロス祭り、サビオはシュート祭りを開催。ヴィッセル神戸のゴールに迫りまくる浦和レッズの姿勢はボールを保持して試合をコントロールする姿勢からは遠く離れたものとなった。もちろん、ネガティブな意味ではない。
非保持でもプレッシングでヴィッセル神戸に襲いかかることに成功する。ロングボールの起点作りに長けているヴィッセル神戸に対して、浦和レッズは442を維持することなく柔軟に対応することができていた。よって、ビルドアップの出口を捕まえ続けることに成功していたこともあって、相手のボール保持者への圧縮へとつながっていった。そのためか汰木が関根に延々と潰され続ける展開になる。渡邊凌磨と安居のボール奪取の勢いも半端なかった。
442のプレッシングの肝は、1列目がどれだけ誘導できるか?にかかっている。サンタナ、松本が判断を間違わずに相手の中盤を消すことを優先する、ここは二度追いする、キーパーまで行く、後方のサポートを待って追いかけすぎないの判断が秀逸だったことは見逃せない事実だった。
浦和レッズが勝ちそうな展開だったけれど、前川のファインセーブを筆頭に最後の最後でひとさしを具現化するヴィッセル神戸の底力も知る試合となったとさ。最後に西川が止めなかったら浦和レッズの負け試合になっていたなんて信じられないぜ。
川崎フロンターレ対名古屋グランパス
思ったよりも差がついた試合。この試合も決定機がすべて入ってしまったでござる試合かというと、そんなこともなかった。
非保持で名古屋がほぼマンマークを行ったことで、この試合は三國対山田というシンプルな構図へ。どうせなら山口瑠伊までプレッシングに行けばもっと面白かったけれど、名古屋にそこまでの狂気はなかった。というわけで、山口瑠伊によるロングボールチャレンジが繰り返されることとなった。
ほぼマンマークでも強引にビルドアップをしていくかなと思ったが、今季の川崎はそういう無理はしないようで、シンプルなサッカーに終止する。三國対山田のマッチアップはどちらのチームも許容できるような結果となった。どちらかといえば、川崎に分があったように感じたけれど、名古屋からすれば、他の場所を動かしてまで、、といったところだろうか。その気持もよく分かる。
名古屋もは原の位置を変えながら優位性を見出していこうと画策するが、川崎の442の前に良い答えが見つけられないようだった。浦和と同じように、川崎の1列目も判断とハードワークを両立させたこともあって、名古屋からすれば思ってたんと違う!となっただろう。マルシーニョがあんなにプレッシングで機能するなんて驚いたぜ。これだったら永井を走らせたほうがと安易な道を選んだほうが結果が出そうな展開へとなっていく。
セットプレーで試合が動いたあとは、川崎がやりたい放題へ。特に2点目はベストゴールに選びたいくらいだった。昨年のスタジアムで川崎を観た感想は、個々の選手の上手さだった。なんだかんだ上手い。それはこの試合でも発揮され家長時代ほどの密集はないけれど、川崎らしいパス回しでの攻撃は健在なんだなと。特に気になったのは山本、河原コンビ。このコンビ以外でもこんなにバランスよくできたらえぐい。
ある程度は誰でもそれなりにできる状態を作るためのプレー原則なのだけれど、お前が支えていたのか!!!になるのはもう少し観てみないとわからない。名古屋は得意のハードワークが空転したというよりは発揮できず。ガンバに少し似た敗戦だったかもしれない。こんな日もあるというか。
ひとりごと
福岡対柏と湘南対鹿島は明日。というわけで、淡々と燦々と続けていきたい。そして急にマッチレポを書いてびっくりさせたい。誰を?

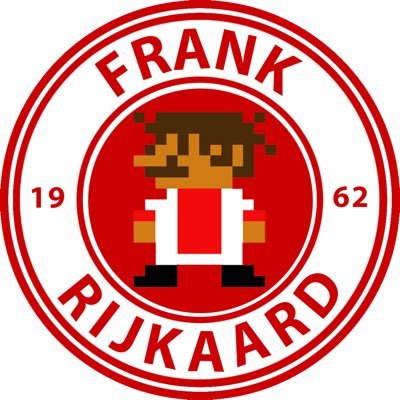
コメント